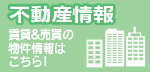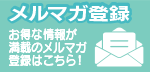ローカルパートナー企業と共にミンダナオ島の開発を手掛ける

長大フィリピン・コーポレーション
社長
加藤 聡さん
1974年東京生まれ。早稲田大学卒業後、1997年教育出版大手の旺文社に入社。2004年より豪州最大の投資銀行のマッコーリー・グループ、2009年に株式会社長大へ。現在、経営企画本部財務・法務部長兼長大フィリピン社長。修士(経営学)、修士(経済学)。東洋大学博士(国際地域学)。2018年より東洋大学国際共生社会研究センター客員研究員。
〈心に残っている本〉
小笹芳央・小畑重和著『「アイ・カンパニー」の時代』です。日本で「リストラ」が新聞紙上を賑わせ始めた頃で、30歳に近づく時期に読みました。自分自身(I)を会社に見立てて、自分のビジネスマンとしての価値や差別化といったことを考えるきっかけになりました。
今年創業50周年を迎えた長大は、この5月にミンダナオ島・ブトゥアン市でパートナーのエクイパルコ社らと開発を進めてきた小水力発電所の竣工式を迎えた。現在はインフラ整備から工業団地の事業まで、ミンダナオ島で雇用創出を通じた民間主導の経済開発を目指して尽力している。その事業を一から手掛けてきたのが加藤さんだ。
編集部
大学を卒業して最初に就職したのは旺文社ですね?
加藤さん
旺文社は教育出版社で、大学受験向けを中心に辞書や教材、英検などの資格試験対策書などをつくっています。もともとマスコミ業界に興味があって、入社試験を受けた一社が旺文社グループでした。学ランで説明会に行ったのが功を奏したようで(笑)、気が付いたら最終面接まで進み、内定をもらいました。
編集部
早稲田大学の第一文学部の哲学科を卒業とあります。
加藤さん
栃木の佐野日大高校というところでラグビー部に所属していて、ラグビーの早慶戦や早明戦を見て、早稲田大学の校風に憧れました。自分のラグビーのレベルは分かっていましたので、プレイヤーとしてではなく、早稲田の学生として早稲田のラグビーを応援したいと思ったのが志望動機です。
哲学科の方は、高校時代に同い年の従兄弟が白血病で亡くなったことがきっかけです。そこで生きるとか死ぬって何だろうとか、人生についてあれこれ考えたわけです。受験勉強の合間に哲学関係の書籍を読んだりしていました。高校の先生には、男が文学部に入って就職はどうするんだとか反対されましたけど、両親は「あなたが行きたいところに行けば」と完全に放置でしたね(笑)。
編集部
入社試験に「学ラン」というのはどういうことですか?
加藤さん
早稲田に入学したものの、いわゆる燃え尽き症候群になりました。とにかく早稲田に入りたい一心で勉強していて、入学したところで目標がなくなってしまったのだと思います。徐々に大学にも行かなくなりバイト漬けの日々になり、あまり大学に行かなくなりました。
入学から数ヶ月経ったある日、母親と大喧嘩をしました。それまで進路には一切口を出さなかったのが、「大学に行きたいというから行かせてあげてるだけで、行きたくないなら辞めたらいいよ」と。泣いていたのも見てしまい、ここでようやく改心をします(笑)。
編集部
改心をしてどうしたのですか?
加藤さん
大学を卒業する時までに、何か1つでも「俺はこれをやったぞ」みたいなものをつくろうと思い、相撲部に入部することにしました(笑)。
編集部
相撲部ですか?(笑)
加藤さん
ちょうど千代の富士世代で、小さい頃から相撲を見るのが好きでした。ただ、生まれてから中学まで東京にいて、土俵で相撲をやったことがなくて、それでただ興味本位で体育の履修科目で相撲を選択したんです。
インカレなどの相撲の団体戦は5人必要なのですが、早稲田の場合は、推薦で入学して相撲部に入る入部者だけでは5人揃いません。とはいえ、一般受験で早稲田に入って、わざわざ体育局(体育会)の相撲部の門を叩く強者というか変わり者もそうはいない。そこで一般入部者の草刈場が、体育の相撲の履修者になるわけです。体育の相撲の履修は、スキーなどの人気科目の抽選に外れて流れてきたか、私のように第一希望で履修する学生に二分されていました。入部してから分かるのですが、運動神経が良さそうな学生に甘い言葉をささやくんでね、「授業最優先、就職心配不要」みたいな(笑)。
編集部
それで相撲部に入部するわけですか?
加藤さん
短絡的ですがその通りです。中学校までずっと野球をやっていて、高校でラグビーをやって、運動神経も悪くなかったと思います。相撲も面白くて、授業はサボりがちでしたが、体育の授業だけは好きでちゃんと履修していたんです(笑)。当初から勧誘を受けていたこともあって、寮にも入り相撲部での新たな生活が始まりました。
編集部
相撲部に入部してからの大学生活はどうでしたか?
加藤さん
入部当時は65キロくらいでした。ちょうど立教大学をモデルにした周防正行監督の「シコふんじゃった。」が1992年に公開された後で、周囲の友人は早速感化されたのかと笑っていました。
下級生の頃は先輩方が強かったですし、そこまで稽古には熱心ではなかったです。ただ、同級生もいなくて、4年生になったら主将としてチームを引っ張らないといけなくなるということを徐々に自覚し始めます。体重もそれでも大きくはないですが、ピーク時で85キロは超えるようになっていて、試合で勝てるようにもなってきて、強くなりたいと稽古に励む、そんな好循環に入りました。
ちょうど舞の海や智ノ花といった小兵の業師が活躍していたこともあり、場所中は「大相撲ダイジェスト」を録画して、下手ひねりとか内無双とか、あまりやる人がいない技なんかで勝った取り組みは、一時停止やスローにしたりして、繰り返し見ていました。だから、寮は相部屋だったのですが、私の部屋には「大相撲ダイジェスト」というラベルを貼ったビデオテープがいっぱいありました (笑)。
ともかく、体が小さいから勝つために技のレパートリーを増やしたいのもありましたが、人があまりやらないということは、相手はそういう技を警戒した体制をしていないので、非常に効果的なんです。こういう差別化は、ビジネスにも通じるところがあるかもしれませんね。ちなみに、私は第78代主将だったのですが、相撲部は今年創部100周年を迎えました。
編集部
話を戻しますが、マスコミ志望で入社した旺文社を辞めるんですね?
加藤さん
旺文社を辞めたのは、入社して6年半位経った頃です。ITが入り始めてきて、新聞や書籍・雑誌といった紙媒体はなくなるくらいなことまでいわれている中で、旺文社は教育出版社で、主要ターゲットは高校生や中学生でしたから少子化という影響も受けていました。世の中的にも、バブル経済が終わり、日本企業に特徴的な「終身雇用」や「年功序列」なども揺らぎ、リストラという言葉が紙面を賑わせ始めていたのもこの頃でした。
会社に頼り切ってはいけない、自分の武器を持って自立しなくてはならないなどと実感するようになりました。一方で、自分自身を振り返ると、大学時代は相撲をやっていただけで、他の学生ほど勉強をしてなかった現実が重くのしかかりました(笑)。
編集部
それが立教大学の大学院に入学した理由ですか?
加藤さん
ちょうど日本でもビジネススクールの開設が増えていました。立教は、社会人を対象にした夜間の大学院で、平日の夜と土曜日に講義があって仕事と両立できるのと、会社から通いやすかったことから選びました。修了したのが30歳の節目を前にした29歳の時です。
編集部
立教の修了と同じくらいのタイミングでマッコーリーに入社されたのですね?
加藤さん
マッコーリー・グループは、オーストラリアで最大の投資銀行で、1990年代からインフラファンドをつくってインフラに投資をしたりしていました。イギリスと共に、公共サービスに民間を積極的に活用して先進的だった国の1つがオーストラリアだったんです。
日本では、2001年に小泉純一郎政権が誕生し、「官から民へ」というキーワードで、道路公団や郵政民営化などの議論が活発化していて、いよいよ日本にもインフラ市場が民間ビジネスとして開かれていくのではないかという期待が高まっていました。マッコーリーが日本でインフラビジネスを始めたのもこの頃でした。
編集部
インフラが民間ビジネスになるというイメージがないですね。
加藤さん
もちろんすべてのインフラが民間ビジネスになるわけではありません。公共サービスである以上、利益の有無に拘わらず、提供されなくてはならないものもあります。ただ、インフラは整備するのに資金が必要ですし、整備後の維持にも資金が必要です。この資金は、誰かが負担しなくてはならず、それは多くの場合、税金になるわけですね。
一方、PPPやPFIの世界に、「バリュー・フォー・マネー(Value For Money)」という考え方があります。簡単にいうと、同じサービスレベルなら費用負担が小さい方がよく、同様に、費用負担が同じならサービスレベルが高い方がよいという考え方です。一般的に、公共より民間の方が、ビジネスや組織を効率よく運営するのは得意だといえます。そう考えると、バリュー・フォー・マネーを大きくするために民間がインフラ事業でやれることはたくさんあると思います。
編集部
インフラビジネスのどういったあたりに魅力を感じたのでしょうか。
加藤さん
当時も「国の借金」が議論になっていて、少子高齢化がもっと進んで社会保障費が増加していけば、日本の財政はどうなるんだろうといわれていました。でも、公共サービスは維持されなくてはなりません。海外での先進的な取り組みやノウハウを日本に持ち込むことに、国や地方自治体の課題の解決にも役立てるのではないかという点が魅力的に映りました。インフラ事業を通じて、会社として利益を上げながら、世の中の役に立てるのではないかと思ったんです。
編集部
そもそもマッコーリーにはどういう経緯で入社するのですか?
加藤さん
たまたま立教で会計学を教えていた先生がマッコーリーで顧問をやっていて、その先生の紹介です。マッコーリーのことは当然知りませんでしたが、事業内容を聞いて直感的に面白いことをやっているなと思いました。ただ、「金融は未経験だし、しかも外資なのに英語もできないので、採用されないと思います」と断ると、その先生は「断るのは採用する側です。興味があるなら、とりあえず話だけ聞いてみたらいいですよ」と。その言葉に納得して、とりあえず話だけでも聞きにいくことにしました。そして、履歴書を準備して面接を受けることになるのですが、ところがここでもまた相撲が絡んでくるのです(笑)。
編集部
マッコーリーでの面接と相撲がどう関係しているのですか?
加藤さん
相撲にも柔道のように段位があって、資格を書く欄に「相撲弐段」と書いていたんです。すでに体重は元に戻っていましたが。でも、相撲ってすごいなと思いました。日本人とか国籍を問わず、面接でもこの相撲に引っかかるわけです(笑)。そんな話もしながら、何度か面接を重ねて内定をもらいました。
編集部
縁というのか、どこでどう物事がつながるか分かりませんね?
加藤さん
はい。ただマッコーリーからのオファーは、半年間だけのものでした。英語も金融も未経験でしたから、その半年の様子を見てその後の契約延長を考えると。半年後の保証はないけど、それでもよければどうぞと。。
編集部
そういうオファーを受けてどうするのですか?
加藤さん
やはり悩みました。ただ、こんなチャンスは人生で2度とないだろうと思い、ともかく半年間死に物狂いでやってみて、それでもダメならその時考えればいいかなと腹を括りました。
その代わりその半年間は、ものすごくストイックに過ごしていたと思います。仕事以外の時間は、駅前留学など英語の勉強だったり、金融関連の本などを読むことに充てていました。そのお蔭もあってか、無事に半年後に晴れて契約更新となりました。
ちなみに、入社した後に、なぜ未経験の私にオファーをくれたのか聞いたことがあります。当時マッコーリーは、多くの日本人が知らないそれまでの日本にない事業をやろうとしていました。そのため、英語ができるとか、金融機関での勤務経験というよりも、そういう環境でやれるかどうかという人間性に評価基準のウエイトを置いていたようです。あの時、自分は未経験だからと勝手に決めつけて行動を起こしていなければ、マッコーリーでのキャリアは拓けていませんでしたから、「とりあえずやってみる」「とりあえず動いてみる」ことって重要だなと思いました。
編集部
マッコーリーではどのような業務をしていたのですか?
加藤さん
マッコーリーに入社した2004年は、第1号案件として「箱根ターンパイク」を買収した直後でした。第1号案件が失敗するとその後の事業展開が難しくなるので、次の新規案件を探しながら、箱根ターンパイクの現場に頻繁に足を運んで事業改善に取り組んでいました。
編集部
投資銀行でありながら、単なるアドバイザーでなく、実際に投資をしたり、投資後に事業改善のために現場に入り込んだりするんですね?
加藤さん
実際にこれが金融の仕事だろうかと思うような現場仕事も多かったです。利用客を増やすために、どこに案内看板を出すのがよいのかと車で一日中走り回ったり、料金徴収員として料金ブースに入ったり、売店のレジ打ち、レストランで蕎麦なんかもつくったりもしました(笑)。
編集部
確かに投資銀行マンのイメージと離れています。
加藤さん
もちろん投資銀行らしい仕事もしています(笑)。マッコーリーが箱根ターンパイクの次に、2006年に買収した有料道路は、岐阜県と滋賀県にまたがる「伊吹山ドライブウェイ」という観光道路でした。
私がこの案件の担当者だったので、財務モデルをつくって事業計画や提案書類の作成などしていましたし、オーナーとの交渉のほか、弁護士や会計士との協議、そしてオーストラリアの本社とのやりとりもしていました。当時はまだ社員も少なくて、いろいろやらなければならなりませんでした。それが逆に良い経験になったと思います。
でも、何から何まで幅広くやる究極の出来事は、交渉が開始して1年間ほど経った時に起きました。買収完了が近づいてきた時に、譲渡が完了したら現場に常駐するようにいわれました。要は、おまえが儲かるといったんだから、その通りに利益が出る事業に改善をしてこいと(笑)。
編集部
有料道路の現場の事務所に行って仕事をしたのですか?
加藤さん
そうです。事務所は岐阜県の関ケ原町にありました。オーストラリアの会社に就職したのですが、同じ岐阜県の大垣市というところにアパートを借りて、岐阜での生活と勤務が始まりました(笑)。
編集部
道路運営会社での仕事はどうでしたか?
加藤さん
従業員が15名くらいでした。平均年齢は50歳を超えていて、ほとんどが地元の出身です。多くの方が前の会社からの転籍していて、長く伊吹山ドライブウェイで働いてるので、現場のこともよく分かっています。一方、私は最年少で、ただ親会社から来たということで役職は高く、そのくせ伊吹山ドライブウェイ事業の現場の細かいことまでは分かっていませんでした。最初は苦労しました。
編集部
例えばどんな苦労があったのですか?
加藤さん
伊吹山ドライブウェイは、マッコーリーが買収するまでは、独立した会社ではなく、1つの事業部の事業として運営されていました。売上金を集計したりはするものの、決算をしたりする経理部門や総務部門がなかったんです。マッコーリーが買収した後は、新しく会社をつくって道路事業だけを行う体制にしたので、例えば会計を担当する人材の採用が必要でしたし、リスク管理などの面で、オーストラリアの本社の規定に合わせたりする必要もありました。最初の3カ月くらいは休みもなく、毎日朝から晩まで、事務所でパソコンの前に座って仕事をしていました。
一方、現場の人は、パソコンでデスクワークなんてしないですから、私が事務所の中で何をやっているか分からないわけです。私は、休みなく誰よりも働いて頑張る姿を見てもらえれば、自分のことを理解して認めてくれて、みんなも心を開いてくれるだろうと甘く考えていましたが、従業員との溝はまったく埋まらないままでした。総スカンというと言い過ぎですが、「あいつは一体何をやっているんだ」と裏でいわれていたようです。
編集部
そうした状況はどう変わっていくんですか?
加藤さん
数カ月経って、徐々に会社としての体制も整備されてきました。私もデスクワークから解放されるようになってきて、事務所の外に出て現場に出る時間を少しずつ増やしていきました。
料金所のブースに入ったり、売店のレジに入ったり、レストランの厨房にも入りました。現場の担当者からやっていることを教わり、同じことをやりました。そうしていると、お客さんがいない時間に、仕事のことやプライベートのことなどの会話をするようになります。その会話が徐々に増えて、日常業務の中の問題点や改善案なんかも話をしてくれるようになりました。情報が入ってくるようになったんです。
心を開いてもらえたということだと思いますが、現場に立ったり、同じ目線に立つことの重要性を実感しました。それまでにワイシャツを着てネクタイをしていたのも、現場の人と同じポロシャツを着て仕事をするようにしたり、私自身の中でもそれなりの工夫をしました。
編集部
現場での仕事も順調に進んでいったんですね?
加藤さん
それがそうでもなくて、こうして現場でうまくやり始めた一方、本社とかからいろいろいわれることが増えました。なんでメールの返信がないんだとか、電話しても事務所にいないんだとか。現場が山の中でしたからね。指示されたことが現場ですぐにやれなくてあれこれいわれたこともあります。確かに、机上で考えると、いわれていることは当たり前で合理的なことなんです。でも、頭で考えているように現場では簡単に進むものではありません。結局、人と人がやっているんだなと感じましたし、いつも机上の計算通りにいくわけではない。以前に書籍か雑誌で、「おまえが(O)、来て(K)、やってみろ(Y)」の「OKY」という略語が、海外の駐在員たちの間で使われているという記事を見たことがあります。まさに、そんな経験をしたのもこの頃でした。
編集部
事業の改善はどのように実現したのですか?
加藤さん
数字上の事業改善には、大きくコストを下げるのと売上を上げることの2つしかありません。
コスト削減の方は、魔法や裏技のようなものはなく、小さい費用削減の積み重ねで実現しました。そのためには現状維持や過去からのしがらみにとらわれないことが大きかったと思います。その点マッコーリーは完全な第三者でしたから、何か発注する時にグループ会社を使うことも、長いお付き合いだから継続して発注するということもありません。他社にも話をして見積をとってみようとなるわけです。要は、競争原理を持ち込んで単価を下げていきました。
また、施設の中には自動販売機が全部で15台ほど設置されていました。それまでは社員が商品の補充をしたり、売上金の回収やつり銭の補充などをして管理をしていましたが、これを一社独占にする代わりに、フルオペレーションでメーカーに丸投げをすることにしました。社員からは反対されました。A社だけの商品しかないと、B社の商品を飲みたいお客様の満足度を下げてしまいますと。確かにそこだけ切り取ってみるとそうなんですが、お客様はジュースを飲みに伊吹山ドライブウェイに来ているわけではないんです。B社の商品がなければ、A社の商品から似たものを探して飲むはずです。お客様の満足をいうなら、それまで自販機の管理をしていた社員の手が空く分、お客様サービスに当たる人手が増えます。社員が本来やるべきことをやる体制をつくることにもなるわけです。その結果、それまで1本あたり150円の売上だったのが、マージンになったので売上は40円に下がりました。でも、この40円の売上には、社員の時間やコストがまったくかかっていませんから、電気代などはもちろんありますが、そのまま利益になります。むしろ利益は増えました。こういう説明や議論をしながら、少しずつ仕事のやり方などを変えていきました。
編集部
売り上げを増やす点ではどういった努力をされましたか?
加藤さん
売り上げを上げる方は、コスト面のように自分たちでコントロールできるわけではなく、簡単ではありませんでした。今でも継続しているのは、メディアへの情報発信です。プレスリリースを積極的に行い、記事として新聞や雑誌に取り上げてもらうようにしました。広告ももちろん良いのですが、新聞や雑誌の記事になると読んでくれる率が大きく変わります。なるべくメディアに取り上げてもらえるようなイベントも増やしたりして、その告知などもしました。こうしたメディア戦略は、今の長大でのミンダナオの事業でも生かされています。
編集部
当初は苦労したものの、その後はすべてうまくいったんですね?
加藤さん
いえ、成功したものもありますが、その裏で効果がなかったり、失敗して元のやり方に戻したようなこともいっぱいあります。それでも試行錯誤自体に意味があったと思います。成功や失敗も含めて、この現場で学んだことは本当に多かったです。
編集部
そんなマッコーリーから長大に移ることにしたのはどうしてですか?
加藤さん
マッコーリーには6年半ほど在籍したのですが、08年にリーマンショックがありました。マッコーリーへの影響は限定的でしたが、マーケット環境が大きく変わったことで、日本の事業について方針の見直しがありました。
そうした中で、日本のインフラ事業については縮小することとなり、新規案件は中断し、すでに運営していた有料道路事業は引き取ってくれる会社を探すことになりました。私の立場は、事業のマネジメントをしながら、その事業の売却先を探すという複雑な状況になったわけです。そうした売却先を探している中で、買い手候補として出てきたのが長大です。
編集部
どうして長大は買い手に名乗りを上げたのでしょうか?
加藤さん
長大は、国内外における多くの長大橋梁の設計など、土木分野を中心に技術サービスを提供する建設コンサルタントです。「長大橋設計センタ」というのが50年前に設立された時の社名で、橋梁では世界でもトップクラスの技術と実績を有しています。瀬戸大橋、明石海峡やレインボーブリッジなどは、長大が設計で関わったものです。現在の社員構成は技術者が8割を占めており、今では橋梁に限らず、道路、交通やITS、環境など、土木分野における調査計画・設計・施工監理までの建設コンサルティングが主事業となっています。
一方で、国内の公共事業予算は1998年度のピークから減少を続け、2010年度には半分以下の7兆円を下回ってしまいます。現在は7兆円から8兆円レベルで推移していますが、少子高齢化もあり、今後公共事業予算が増加していくと期待することは難しい。そうした厳しい経営環境の中で、安定経営と将来の成長を実現するために、インフラ事業の管理運営などの新事業の開発に注力をし始めていたんです。
編集部
なぜ長大に入られたのですか?
加藤さん
マッコーリーと長大は、私の中では、「インフラ投資」や「インフラ事業」というところで筋が通っているものです。インフラは、整備や維持管理のために資金が必要ですが、資金だけでは不十分で、「技術」の役割が不可欠です。資金と技術は車の両輪のような関係だと考えています。その一方で、資金と技術の間には分断がありました。つまり、マッコーリーのような金融プレイヤーと長大のような技術プレイヤーが完全に分かれているんです。
だから、もしマッコーリーを経て長大に移れば、この両者の間に立てるような人間になれるのではないかと思いました。今さら技術者になるつもりも、技術者になれるものとも思っていませんでしたが、少なくとも両者の人たちと共通言語で会話ができるのではないかと。「知識通訳」という言葉があることを後で知りましたが、こういう異分野を繋ぐ役割ができれば、差別化できて自分の価値にもなるのではないかと思いました。
編集部
長大に入社してからはどんな業務を担当したのですか?
加藤さん
長大では新事業の開発を期待されていました。長大に入社した時は、まだ伊吹山ドライブウェイの買収が完了していませんでしたので、長大での最初の仕事は、買い手として古巣のマッコーリーと交渉をすることでした。半年ほどの交渉の後買収が完了します。同じ有料道路を2回買収することになりました。M&Aに従事している方は日本でも多くいると思いますが、それでも同じものを2回買収した経験を持っている人は少ないのではないかと思います (笑)。また、M&Aにも関わり、当初2年間くらいで数件の買収を完了しました。自社での新規案件の開発にも関わっていて、そのうちの1つがフィリピンの事業です。
編集部
長大に入られて、最初にフィリピンに来られたのはいつ頃ですか?
加藤さん
2011年の9月です。当時通っていた大学院の講義の一環で、調査のために訪問したのがきっかけです。そこはPPPを専門にした社会人大学院で、私は会社派遣で2011年に入学しました。講義科目の1つに、ある自治体を取り上げてPPPを通じて地域の課題解決や活性化について研究する「プロジェクト演習」があり、ここでミンダナオのブトゥアン市を取り上げることになりました。
編集部
ミンダナオがスタートだったんですね?
加藤さん
ブトゥアンは深田祐介の「炎熱商人」にも登場するのですが、もともと林業が盛んで日本にも木材を輸出していました。その林業が衰退し、その後主要産業になったエビの養殖業も、1990年代後半をピークに連作障害や病気で衰退してしまいます。その後、JICAによるODA事業などで建設業が主要産業になるのですが、ODA事業も永久に続くわけではありません。
編集部
新たな産業の創出が必要になってきたわけですね?
加藤さん
ブトゥアン市はミンダナオ島北東部にあるカラガ地域の中心都市です。人口が40万人弱で、ミンダナオ島では5番目、6番目くらいの都市です。大学やカレッジも多く、雇用の受け皿になって地域を支えるような新たな産業が必要でした。長大のパートナーであるエクイパルコ社はブトゥアン市に本社があります。創業者の1人で当時のCOOのラグナダ氏が、ブトゥアン市の出身なのですが、この地域に若い優秀な人材を引き留める雇用創出の場がないとブトゥアンの発展はないという危機感を持っていたようです。ちなみに、そのラグナダ氏は現在、ブトゥアン市の市長をやっています。
編集部
最初にブトゥアンを訪問した時はアキノ政権でしたね?
加藤さん
「財政再建」「汚職一掃」を掲げていて、フィリピンが初めて投資適格国になるなど評価されるべき面がある一方、財政再建のために公共投資予算が抑えられました。インフラは経済成長のベースになるものです。そこで、財政再建とインフラ整備を両立させるために、アキノ政権がもう1つ重要視していたのがPPPでした。つまり、公共投資予算に制約がある中、PPPを通じて民間資金を導入することで、必要なインフラ整備も進めようとしたのです。
編集部
そこからブトゥアンにはどうつながっていくのでしょうか?
加藤さん
ドゥテルテ大統領が就任してミンダナオを取り巻く状況は変わりましたが、当時公共投資の優先順位はマニラ、セブ、最後にミンダナオと続いていました。つまり、受け身で待っているだけでは開発から取り残され兼ねない状況にあったのです。だったら、ブトゥアンでもPPPを使って地域開発を進めようという発想にいたり、具体的にPPPを活用するための助言や支援を求めていたところ、東洋大学PPPスクールとブトゥアンがつながります。そこから東洋大学によるPPP調査の実施が決まり、私も調査メンバーの一員として、2011年9月に現地を訪問することになるわけです。
編集部
そのPPP調査から長大の事業につながっていくのですか?
加藤さん
PPP調査は報告書を作成して終了しましたが、調査報告書は、自社のビジネスであれ、何でも自由に使ってよいことになりました。一方、長大は当時、国内外の新事業の開発にも注力していて、アジアの水力発電事業はターゲットの1つでした。水力発電は事業開発費の6割から7割が土木に関連することから、長大の人材や技術、これまでの実績が反映しやすいからです。エクイパルコ社が同社として初めての水力発電を計画していることを知り、PPP調査から帰国して新事業開発を担当している事業企画部長に報告、翌月すぐに2人で、今度は長大の社員としてブトゥアンを再訪しました。
今では小水力発電に留まらず、風力やバイオマスといった再生可能エネルギーや上水供給などの基礎インフラ、農業や養殖といった一次産業、そして工業団地の開発・運営事業まで広く展開しています。これらの事業はすべて民間事業として進めていますが、長大も出資を通じて長期間コミットするスタンスで取り組んでいます。
編集部
長大もそれぞれの事業に出資をしているのですね?
加藤さん
その通りです。今ブトゥアン周辺では、10以上の事業を進めていますが、事業ごとに会社をつくって、長大もマイノリティ出資をしています。一番最初に出資した案件が、アシガ川小水力発電という8MWの電源開発を行う再生可能エネルギー事業です。2012年に出資をして、長大は10%の出資をしていますが、それから5年近くを経た今年の5月にようやく竣工式を迎えました。
編集部
中長期で一緒にやっていく決断ができたということは、現地のパートナーにも恵まれたということですね?
加藤さん
海外の事業には、国内の事業と違って考慮しなくてはいけないリスクが一段階増えます。その中でも重要なのが、パートナーリスクだと考えています。例えば水力発電事業でいうと、いわゆるネガティブリストといわれる外資規制があり、長大の出資比率は4割まででといったように、外資の出資比率に制限があるのです。出資比率のマジョリティを握ることはできませんので、現地パートナーを信頼して依存せざるを得ないわけです。それも長期間にわたって良好な関係を維持できるパートナーでなくてはなりません。地元出身で地元愛のあるパートナーだったのも決めてになったと思います。
編集部
工業団地事業の開発はこれから進めていくということですね?
加藤さん
はい。小水力発電もそうですが、インフラを整備する事業は、建設期間中は地域の雇用創出効果も大きいですが、一旦整備が終われば仕事はなくなります。継続的に大きな雇用は生み続けるわけではありません。そういう点で、ヒト・モノ・カネが域内で循環し、周辺産業の創出も期待できる工業団地の開発・運営プロジェクトが重要だと考えています。
今はまだ、一部で精米工場が稼働している段階ですが、これから本格的な調査を経て開発に入ります。ブトゥアン周辺地域の優位性を生かすために、一次産業を中心に、ミンダナオの相対的に低い賃金水準を考慮して、労働集約型の傾向がある農林水産系食品加工の工業団地が競争力を持つのではないかと考えています。さらにいえば、日本企業や日本との関わりがあるようにしたいですし、環境面などで日本スタンダードの工業団地にしたいですね。
編集部
工業団地の事業開発が最終ゴールということでしょうか?
加藤さん
産業道路や港湾といった工業団地の周辺インフラの整備も必須だと考えています。なぜかといえば、工業団地で製造や加工されたプロダクトは国内外に流通していくので、それを支える物流のインフラ機能が現状ではまだ不十分です。
ミンダナオもこれから人口が増えますし、経済レベルも上がります。ダバオやカガヤンデオロというミンダナオの第一の都市、第二の都市だけではなく、日本の高度経済成長期の「国土の均衡ある発展」のように、ブトゥアンや他の都市のインフラの開発も進んでいかなくてはいけません。さまざまな都市が機能分担をしていくことが、リスク分散にもなりますし、ミンダナオ全体の発展につながっていくのだと思います。こうした大規模な産業インフラの開発は、民間企業のレベルでどうこうできるものではないですが、その必要性は訴えていきたいと思っています。
編集部
経歴書を拝見すると、今春に大学院を修了されたのですか?
加藤さん
はい、2015年に入学した東洋大学の国際地域学研究科の博士後期課程を修了しました。もともと2011年に大学院で行った調査がきっかけで、今のミンダナオでのビジネスが始まりました。徐々に事業が広がっていく中で、民間ビジネスを通じた「地域開発」をキーワードにして事業展開を進めます。地域開発を語るなら、専門家がいた方が良いに決まっています。でも、長大は土木系の建設コンサルなのでそうした地域開発の専門家がいないわけです。海外では博士号の学位は評価されますし、であれば、自分が専門家になればよいかと短絡的に考えて、大学院に戻ることにしたんです。
編集部
研究テーマはどういうものだったのですか?
加藤さん
開発課題が多様化したり複雑化する中で、公的な支援は特に資金面でリソースに限界があります。だから開発途上国の開発を推進するために、NGOやNPOも含めて、民間企業の役割が重要になってきていて、こうした民間セクターとの連携の1つに挙げられるのがPPPです。一方で、地域開発の手法として活用されるPPPの事例はまだ多くないため、そうした課題の整理や、PPPの活用を促進するための手法などを博士論文でまとめました。ミンダナオの事例も取り上げています。
学問と実務の両面から同じテーマに取り組む機会は珍しいと思います。そんな貴重な機会を与えてもらったこともあり、ブトゥアン、そしてミンダナオにはライフワークとして今後も関わっていければと思っています。
編集部
会社も全面的に後押ししてくれているわけですね?
加藤さん
そうですね、その点は本当に感謝しています。建設コンサルタントの一般的な業務というのは、予算単年度主義もあって基本的に工期も売上も1年単位で動いていきます。一方で、ミンダナオの取り組みは、出資をして中長期にわたって事業を行って、少しずつ投資資金を回収して、その後ようやく利益貢献につながるものです。時間軸が圧倒的に異なります。会社の理解がなければとても進められるものではないんです。
長大のフィリピンのミンダナオでの取り組みは、新事業の象徴のようになっていますし、同業他社からも注目をされています。業界の新しいビジネスモデルの事例になればとも思います。また日本でも地方創生が注目されています。面的な地域開発の実績で得たノウハウなどを、日本に逆輸入するようなこともあり得ない話ではないだろうと思っています。
編集部
加藤さんご自身はフィリピンに長くいられるおつもりですか?
加藤さん
最初にフィリピンに来たのが2011年ですから、7年近くビジネスをしていますが、駐在したことはなくずっと出張ベースです。2013年に駐在員事務所を設立して所長になり、2017年に現地法人を設立して社長になりましたが、いずれも東京の本社との兼務になっています。
「駐在はしないのですか?」とよく聞かれますが、個人的には、この出張ベースの仕事の進め方が合っていて、これまでこのスタイルだからこそうまく進んでいるのだと考えています。どういうことかというと、ミンダナオの事業はビジネスのスピードが早く、まだ安定運営にいたっていないステージにあります。私自身が動いて、私自身の五感によってインプットしたものを、フィリピンでも日本でも、社内でも社外の人でも、私自身がアウトプットすることができます。つまり「私が見た」「私が聞いた」という「私」を使った一人称で話すことができるんです。微妙なニュアンスや温度感も含めて伝えられますから、伝わりやすいですし、結果として物事を進めやすくなっています。
編集部
これからフィリピンに進出してくる方に一言。
加藤さん
フィリピンに関する情報が限られていたり偏っていたりして、特に治安の面で誤解されて、敬遠されてきました。とにかく一度来て自分の目で見て欲しいですね。英語で仕事ができますし、親日的で明るく、何より物理的に近いところです。フィリピンは日本人にとって仕事のしやすいところだと思います。
編集部
座右の銘は?
加藤さん
最初に入社した旺文社の創業者である赤尾好夫の言葉で、社是の冒頭の一部にある「夢高くして足地にあり」という言葉です。個人であれ会社であれ、夢や目標は必要です。一方で、夢や目標があまりに現実離れした理想論になってしまえば、実現できない画に描いた餅になってしまいますし、逆に現実的過ぎて低すぎる夢だと成長や進歩がありません。バランスが重要だと思います。
編集部
今後の夢や展望は?
加藤さん
フィリピン全般にいえますが、特にミンダナオの情報はあまりないので、特に治安面でフィリピンに対するネガティブなイメージが日本にはまだ根強く残っています。ミンダナオには大きなポテンシャルがあって、日本企業にとってのビジネス機会にも恵まれていることを、今取り組んでいる事業を通じて発信していきたいです。そして、人が新たな人を呼び、金が新たな金を呼ぶと考えているので、多くの日本企業に入ってもらいたいですね。幅広く多岐にわたる事業を展開していますので、長大と現地パートナーだけで全部をやれるわけではありません。事業ごとに得意な技術を持っているパートナーを巻き込みながら、最強チームをつくってやっていきたいと思っています。
長大という社名は、「長大橋梁」に由来しており、橋の設計からスタートした会社です。事業を通じて、人や地域を繋いだり、今と将来を繋ぐような、そういう日本とフィリピン、日本とミンダナオを繋げるようなことができたらいいなと思っています。